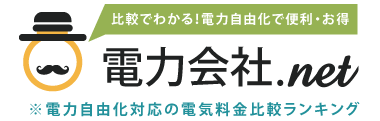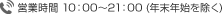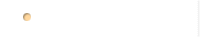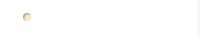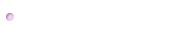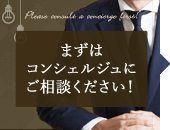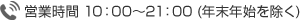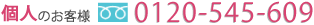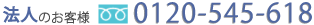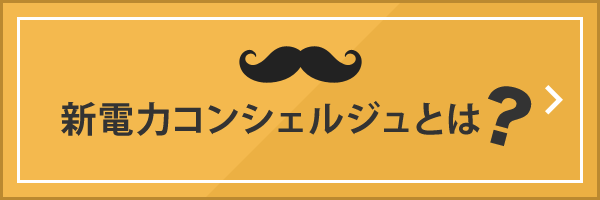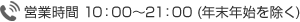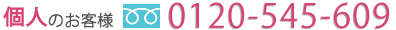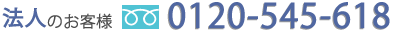電力自由化の経緯
電力自由化の経緯
電力自由化の背景

電気は、水道やガスと併せて国民の生活を守るために必要とされている重要なインフラのひとつです。
日常生活を満たすため、停電が起こることなく電力を各家庭に配分した上で、適切な電気料金を徴収しています。
全国各地域の発電および送電を担う存在として、東京電力をはじめ電力10社が経営を行っています。
電力会社は民間企業にあたりますが、インフラを担う性格上、国の規制も多い業界として半ば公的機関の性格も持ち合わせており、消費者側としては地域の1社のみが電力供給企業として供給を受けることができました。
民間企業であるにも関わらず、市場で競争が働かないことから、電気料金は高止まりの一方であり、市場の原理を働かせてこれを解消すべきという声が集まってきました。
こうした背景を基に、1993年には当時の総務省において、エネルギーに関する規制緩和の提言が行われてきました。
自由化の経緯
エネルギーに関する規制緩和の提言以降、国・企業・国民を合わせてさまざまな意見や討議が重ねられた結果、段階的に電力自由化が実施されてきました。
まず、1995年には、31年振りに電気事業法が改正され、発電事業へ新規参入が拡大されることとなりました。
これによりIPPと呼ばれる独立系発電事業者が電力を供給する事業に参入することが可能となりました。
次に、「経済構造の変革と創造のための行動指針」によって1999年に電気事業法が改正され、大規模工場やデパートを対象にPPSと呼ばれる特定規模電気事業者の新規参入が可能となりました。
そして、2003年の電気事業法改正では、供給システムの安定性確保とお客様の選択肢拡大を背景に、卸電力取引所が創設されました。
今後
こうした背景や経緯をもとに、電力自由化の流れは工業や商業といった大規模施設のみならず、私たち一般家庭においても選択肢が広がっています。
2016年は、「電力自由化元年」とよばれるほどの大きな規制緩和が施行されることが決定されており、一般家庭でも電力の供給企業を選択することが可能になります。
これにより、毎月支払っている電気料金を格安に抑えることが見込まれており、また、他のサービスとセットで加入することでさらなる割引を受けることができると予想されています。